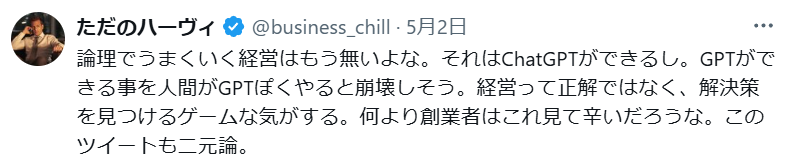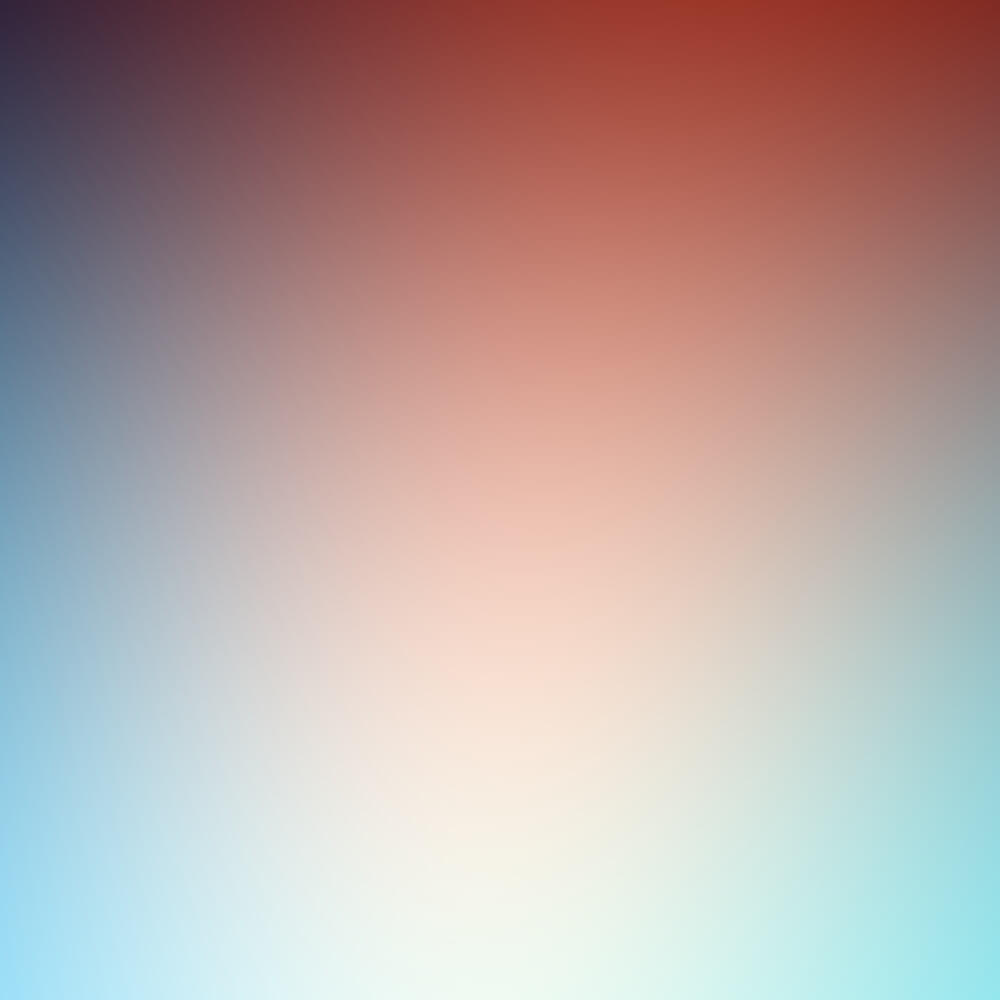💓
感情と合理性 - 感情だよ。
あるnoteの記事がバズっていた。
外部から事業会社の経営に招聘された人物が、(おそらく)株主からの変革期待を背負い、スピーディな改革に着手したものの、現場との信頼関係構築を怠ったことで社内からの反発を招き、結果として成果を出せずに終わった——そんな出来事が赤裸々に綴られていた。
タイトルには「雇われ社長」とあるが、その内容は、単なる経営者の話にとどまらない。中途入社、M&A後のPMI、あるいは社内異動など、“外から来た人”が新しい組織に入っていくすべての場面で起こりうる話だ。記事は一度大幅にリライトされたが、最終的にはこんな言葉で締めくくられていた。
半年は何も変えず、現場でとことん学ぶ。今なら「何を変えないか」を見極めることから始める方が、成功に近づける気がしている。
“外から来た人”が組織の中に飛び込み、短期間で成果を出すことの難しさは、想像以上だ。経営に限らず、新しい環境で何かを動かそうとする人すべてにとって、他人事ではない話だ。だからこそ、このnote記事が、これほど多くの議論を呼んだのだと思う🤔

自分は今、連続的なM&Aを中核戦略とするGENDAにおいて、事業開発(以下、BizDev)の立場からグループ各社に参画し、事業や経営の責任を担っている。
GENDAに入って間もない頃、短期的な成果やアウトカムだけを強く重視する空気感と、少なからず緊張関係があった。短期の成果を追うこと自体は当然のことだと、自分も思う。その一方で、自分は今も昔も変わらず、まずは、信頼構築を最優先に据えるべきだと信じている。
なぜなら、組織の複雑さの本質は、戦略や施策の前に、人の感情や、目には見えない力学にあるからだ。どれだけ合理的で正しい施策であっても、そこに関わる人たちの理解や共感、信頼が伴わなければ機能しない。感情の機微に丁寧に向き合わずに推進を図っても、実行の質は下がり、スピードも落ちる。
だからこそ、まず向き合うべきは、合理ではなく、感情なのだと思う。推進とは、ただ物事を前に進めることではなく、人を動かすこと。人を動かすとは、感情を動かすこと。
現場に入り、空気を吸い、人を知り、関係性を築く。戦う前に、変える前に、まずは知り、そして受け入れる。その方が、結果的に早く、質の高い成果を生むことができる。これこそが、“外から来た人”が新しい組織で最速で成果を上げる、一番の近道なのだと信じている。
自分のプレイブック: 推進とは何か?
自分が仕事で向き合っている「推進」という営みには、明確な3つの要素があると思っている。
それは、①感じ取る力、②信頼構築力、③実行力だ。
前提として大切にしていること
- 「推進」は、この3つが欠けると成立しない。
- 体力とメンタルは超重要。特にメンタルは、後天的に育つものではなく資質に近いと考えている。嫌われることを恐れない、自分を信じる、孤独に負けない──この3つは最低条件。
- 「自責であること」(=ラストマンシップ:事業および経営において、常に最終責任を負うマインド)は鉄則。
- 綺麗にいくことなんて、ほぼない。当事者にしかわからないことも多い。本に書いてある通りに進むことなんて、現場ではまず起こらない。結局は、その場その場を自分の感性と経験で乗り越えるしかない。
① 感じ取る力
- 最も重視しているのが、組織とヒトの理解。
- 特に、「組織の力学」や「人心の機微」を読み取ることを徹底して行う。
- 全社員との1on1、各種ミーティングへの参加、飲み会なども含む。
- ただしミーティング参加ひとつ取っても、簡単ではない。1on1も順番や組み方も含めて戦略がいる。
- たとえば、
- Aさんはこういうトピックによく反応しがち、
- Bさんはこういうトピックのときに表情が曇りがち
- Cさんがどういうことに力を及ぼしているか
- Dさんはこのシーンでは発言するけど、このシーンでは発言しないな
- Eさんの発言から、こういうことを感じてそうだな
など、細かい観察と仮説を繰り返す。
- 頭の中に「社内相関図」が描ける状態をつくるのが目標だが、同時に、その個人個人の思考や感情の癖を捉えることを意識する。
- 組織には常に政治があるし、変な人もいる。でも政治に勝とうとしてはいけない。勝ちにいくと飲み込まれる。
- ロジックも大事。でもエモーションはもっと大事。防衛本能に強弱はあれど、人はテリトリーの侵害や、変化に強くない。
- そして、「組織の力学」や「人心の機微」は、外からは絶対にわからない。
② 信頼構築力
- 信頼を得るには、
- 「こいつ分かってるな」と思わせること
- 期待値を超えること
が必要不可欠。
- 「現場にいること」は信頼構築の強力な手段。辛さがわかる、同じ経験をしている──ただそれだけで届く信頼がある。
- 共に時間を過ごすことも大切。焦らず、地道に関わり続ける。
- 「感じ取る力」をもとに、意図を持ったコミュニケーション設計をする。
- 会議で反応が微妙だった人に、あとで個別に声をかける
- 頼られていないと感じてそうな人に、あえて会議中に意見を求める
- ときに相手を動かすために、挑発的な一言を入れる
- 「今はここまでが適切だ」と判断して一歩引く。タイミングや距離感。
たとえば:
- あわせて、「受け身の貢献」も大事。相手が求めているであろうことに対して、圧倒的な量かスピード──いずれかで期待値を超える。驚かせる。
- この過程を通して「仲間」ができる。この人信頼しはじめてくれているな、とか。信頼は0→100ではなく、段階的に生まれる。
- 経営上の意思決定に信任を持たせる方法も常に意識する。これは「誰を仲間にするか」のウエイトも非常に大きい。
- ここまでやって、ようやく「実行に移すための基盤が整った」と言える。感覚としては8〜9割、ここで決まる。
- この記事を読んでいて思ったのは、「最初から改革前提で入っていくスタンス」は、現場にとってはこれまでの積み重ねを否定されたように映ることが多く、リスペクトを欠く可能性がある。①、②も含めて、推進力であり、社員の信頼や尊敬の獲得こそが、推進のほぼすべてなのだと思う。
- なお余談だが、自分はお酒が飲めない。「酒」や「寝技」だけが信頼構築の手段というような考え方は、稚拙で短絡的だと思っている。それ以外にも方法はいくらでもある。
③ 実行力
- コメントは多くない。淡々と実行し、軌道修正しながら、サイクルを回していくだけだ。
- 優秀な仲間もいれば、変なアクションにはならない。正しく頼ることで、チームは本来の力を発揮する。
- 焦らず、地道に、着実に、ただ進めればいい。
GENDAのBizDevでは、「状況判断力とバランス感覚を備え、組織の力学や人心の機微を適切に読み取ることができること」を必須要件として掲げている。これらの必須要件は、BizDevの仲間たちと徹底的に議論し、言語化したものだ。他社の採用基準でも、ここまで言い切っている例はそう多くないと思う。

個人的なバイブル書籍です。本を読んだからってできるようにはならないんだけどね。

最後に
今回の記事は、自分自身の「プレイスタイル」をあらためて見つめ直す契機になったし、いつ自分が同じ状況に置かれてもおかしくないことを考えると、肝に銘じておくべき出来事だと感じている。そして、こういうテーマ──組織の力学や人心の機微に焦点が当たる話は、なかなか表には出てこない。だからこそ、あの記事が公開された意義は大きかったと思う。実行だけに注目が集まりがちな中で、その前段にある「感じ取る力」「信頼構築力」こそがAI時代に代替されにくい、最も人間的なケイパビリティなのだと思う。
(記録用)引用リツイートの抜粋